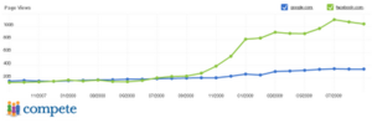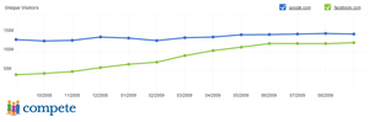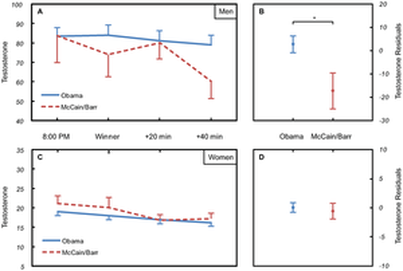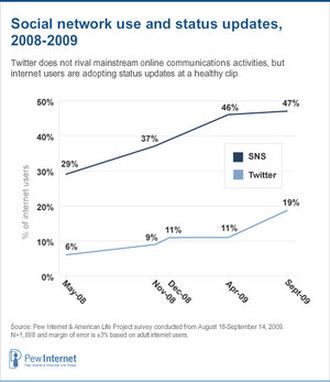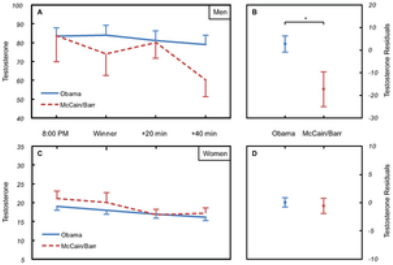世界同時にマイケルの「スリラー」を踊ることがポイントで、17時半直前にカウントダウンが始まりました。目的は、私が住んでいるAlemadaのホームレスへの寄付集めにありましたが、ハロウィーンの時期でもあり、グローバルなダンスマラソンに、地元のTV局のカメラも入り、大いに盛り上がりました。
ここで踊っているのは、クラスメイトやその家族で、プロのメークアップアーティストにメイクをしてもらって、みんなかなり迫力ある「ゾンビの顔」で踊っていました。早速、YouTubeにヴィデオがあがっています。ヴィデオの中で、私は最初のカウントダウンと途中の叫び声を担当(笑)、さらにダンス終了後の7分以降に座っている観客の中で、瞬間映っています。老いも若きも参加して、家族ぐるみでコスチュームを着てスリラーを踊る姿を見て、「参加する」コトをエンジョイする米国人の楽しみ方を実感します。