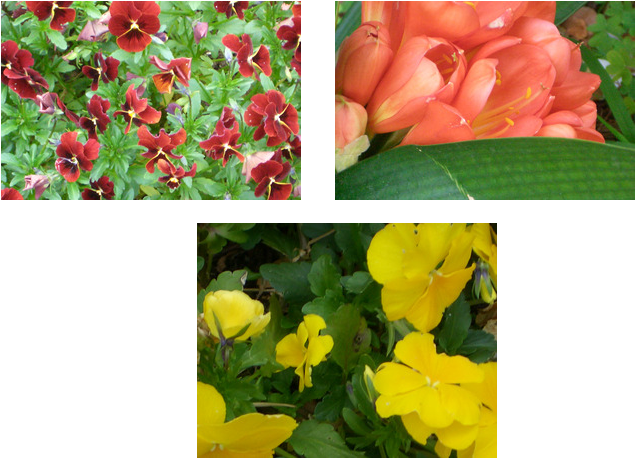子供の時に、夢見た職業は何か?
私は小学校の卒業文集で、「どんな職業に就きたいか?」という質問に対して
「宇宙飛行士」と答えました(絵をつけて書いています)。
当時、すでに仮性近視の傾向が出てきて、メガネが必要となりつつあった私は、近視では宇宙飛行士になれないと知って、中学生になると、あっさりとこの夢を捨てて、「ジャーナリスト」になりたいと、コースを大きく変更したのを覚えています。結果40年近くを経て、ジャーナリストではありませんが、本も出版し、こうして毎日文章を書く仕事をしており、中学生時代のDream Jobに、たどり着いたといえるかもしれません。
アメリカ人の子供の時の「Dream Job(夢の職業)」は、こんな感じです。
- 59%の弁護士・判事、24%の教師: 「大統領」
- 41%の消防士と警官、29%のエグゼクティブ: 「消防士」
- 22%の製造業勤務者: 「カウボーイ」
- 33%の事務職: 「プリンセス」
- 33%の看護婦、28%の主婦: 「プロフェッショナル・ダンサー」
この現在の職業と子供時代の夢の職業の相関関係が、中々興味深く、弁護士の大統領志向と、事務職のプリンセス志向は、思わず納得してしまいます。半分近くの消防士は、初志貫徹で、子供の頃の夢を具現化しており、これは、素晴らしいなと思います。
私も小学校の低学年の時には、手塚治虫の「リボンの騎士」のサファイア姫に憧れて、プリンセスになるんだったら、彼女のように剣術と馬術が上手で、騎士となって敵と立ち向かうんだと、弟相手にフェンシングの練習をしていたのを思い出しました。サファイア姫は、天使のいたずらで、男の子と女の子の両方の心を持ち、跡継ぎの男子のいない王国のためにプリンスとして、育てられるというストーリーで、私の大のお気に入りでした。
当時は、女の子は「大きくなったら、お嫁さんになるの」という返事が全盛だった時代で、私がサファイア姫に憧れた大きな理由は、「男の子になれる」という部分だったと思います。我が家は祖父母の代からの果物屋の自営業でしたから、祖母、叔母、母も含めて、男女の区別なく、みんな働いていました。ただ、時代は男女雇用均等法以前のずーと昔で、まだまだ女性のプロとしての職業が多く確立されておらず、子供ながらに、女性として自立することに対する漠然とした不安が、「リボンの騎士」に変身できるサファイア姫への憧れにつながったのだと思います。
男の子になる必要もなく、プロとしての職業を得ることが出来た私は、本当に幸運だったと思います。また、「夢」を言葉で語っていくと、きっとそれが実現します、それは私の50年間のWisdomです。