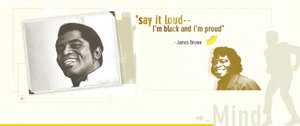いつものように、ラスミニッツで掃除やらNew Years Eveの準備(Dinner & 年越しそば)をして、あっという間に夜に突入しています。夫と2人で、クリスマスに亡くなったJames Brown(JB)のBest Live Album 「Live at Apollo in 1962」を、iTunesで9.99ドルで購入して、たった今ダウンロードし終わったところです。今夜は自宅で年越しそばを食べながら、このJBの名作を聴きながら、2人で新年のカウントダウンのパーティをする予定です。
このアルバムも、私たちはわざわざ地元のレコードショップにフィジカリーに歩いて買いに行きましたが、当然のごとく、在庫はなく、JBのトリビュートコーナーもない始末。音楽は、すでに完全にオフラインからオンラインへ移ったことを実感します。2人ともOld School(古いタイプ)ですので、CDのアルバムジャケットも欲しいと言って、これはアマゾンにオーダーしてCDそのものを買う予定です。iTunesのトップページでは当然、JBのトリビュートコーナーが最初にあり、ユーザが今欲しい旬のものがパッと買えます。
Instant Gratification(瞬間的な満足)という言葉が、今の時代のキーワードです。「待つ喜び」をすっかり忘れてしまった私たちは、2006年最後の日も、相変わらずオンラインショッピングをしています。
今年最後のブログです。読んでいただいた方に心からお礼を申し上げます。来年が皆さまにとって、すばらしい年でありますように、心からお祈り申し上げます。
大柴ひさみ