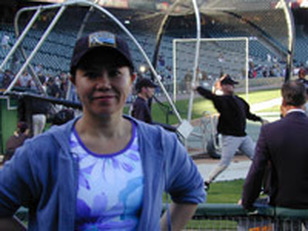ただ、そんな中で、打ち合わせを終えて、LAX(ロスアンジェルス空港)の中のバーで1人、飛行機を待っていた時に、いきなり顔を手で覆って泣き出した女性を目撃しました。
メキシコ系の彼女は、私がワインを注文した後に、コロナビールを頼み、お互いにちょっと眼があって、にこりと微笑んだ女性で、3つの大きな買い物紙袋を持 ちながら、携帯電話で熱心に何かを話していました。私がワインを一口飲んで、バーの上にかかっているTVでハリケーンRitaの様子を見た後、何気なく彼 女に視線をうつしたところ、彼女の崩れるような泣き顔を見てしまいました。
「家族や友人に不幸があったのか?」、「職場で突然レイオフされたのか?」、「夫に裏切られたのか?」、「子供が犯罪を犯して警察につかまったのか?」な ど、ありとあらゆる泣きたくなるような状況を一瞬考えながら、見てはいけないモノを見てしまった罪悪感にとらわれ、私はあわてて視線をワイングラスにうつ しました。
空港には、本当にいろんな人生があります。カウンターでは、見知らぬ人同士の白人女性とラテン系男性が楽しげにおしゃべりを始めており、私の横のテーブル 席のインド系の男性はラップトップに何か熱心に打ち込んでおり、向かいの4人は飛行機の出発時間が近いのか、あわてて食べている、そんなさまざまな情景 が、まるで映画のように、私の目の前を流れていきます。
私は、そんなさまざまな人たちの人生が進行する夜の空港で、悲しさに張り裂けるような表情で、泣き崩れた女性の顔が忘れられず、思わず私自身、涙があふ れ、それを隠すために、うつむいてしまうほどでした。「なんでそんなに悲しいの?人生は必ず良い方に転がっていくから、心配しないで。あなたは必ず幸せに なれるわ」と言って、思わず抱きしめてあげたい、そんな思いで一杯になりました。
日頃は自分のビジネスに追われていて、なかなか出てこない、非常にセンチメンタルな感情が、珍しく私を満たし、これも、「Buyers Remorse」の一つの症状かしらと思いながら、帰りの飛行機に乗り込みました。