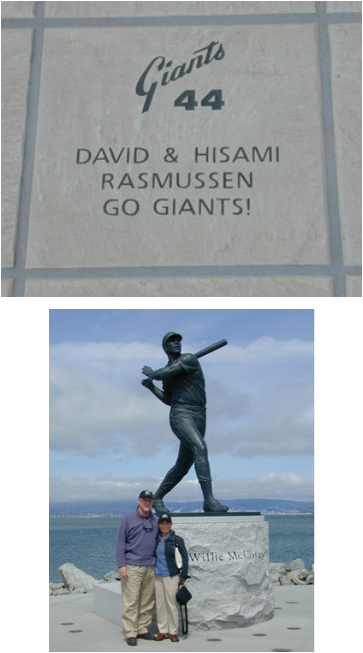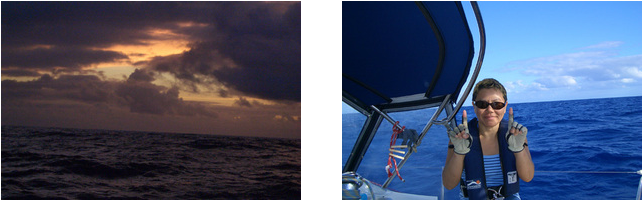SF Chronicleの6/26付けの記事に よると、ゲイのメッカCastroの有名なバーBadlandsが、アフリカ系アメリカン人のゲイに対する人種差別で、4月以来SFの人権保護団体の調査 を受けていることに関連して、すでに8週間、継続的な人差別反対のデモンストレーションのピケが張られていることを報道しています。問題はSF名物のゲイ パレードを前に深刻化していることをポイントアウトし、ゲイマリッジを実行して一躍全米中に名をはせた現SF市長のGavin Newsomは、アフリカ系アメリカ人の前SF市長Willie Brownに、この問題の仲裁を依頼したということです。
ゲイコミュニティでの差別は、今に始まったことではなく、Castroでは、白人ゲイによるアフリカ系アメリカ人のゲイ、および女性のゲイ(レズビアン) への差別は公然と行われています。記事によると、SFに20年間住むアフリカ系アメリカ人の52歳のレズビアンは、Castroのストリートで、 「Big, Black Nigger, Bitch」という、ちょっと信じられないような差別用語で呼ばれたことがあると告白しています。
悲しいことに、「差別され続けている人たちの中には、そのマイノリティとしての苦しさの代償作用として、今度は自分が差別する側にまわることを求める」よ うで、ゲイコミュニティにおける差別の階層は、よりマイノリティである、アフリカ系やアジア系のゲイ、さらにレズビアンや性転換者など、多層化した構造を 持ちます。ちなみに人種だけに限らず、年齢に対する差別も存在するらしく、「若くて美しい肉体を持つゲイ」を求めるコミュニティでは、年齢を経て肉体が衰 えてきたゲイには、厳しくむごいAttitudeが多く見られるらしく、ゲイのメッカ「Castro」を離れるケースも増えていると、聞きます。
これもゲイに対する社会的認知の向上が一役買っており、通常のコミュニティにおいて、ゲイ自体がすでにマイノリティとして特別視される時代が終わり、彼らは単に「セックスのオリエンテーションが違う人たち」として、社会が受けて入れている現状を反映していると思います。
アメリカは「差別を議論する、あるいは議論したい」国です。この言葉なくして、アメリカを語ることはできません。差別をアンダーグランドに封じ込める文化よりも、それをパブリックで、何でも話しあう文化の方が、個人的には好きです。
うちの夫の前妻の姉もゲイで、昨年オレゴン州でゲイマリッジを行っています。若い頃から、彼女を知る夫は、「彼女と僕の考え方は非常に異なるが、なぜかと ても気が合い、好きだ」と言っています。私は彼女がクリスマスに必ず贈ってくるハンドメイド・クッキーの大ファンで、まだ会ったことはありませんが、是非 会って話してみたい人の一人です。