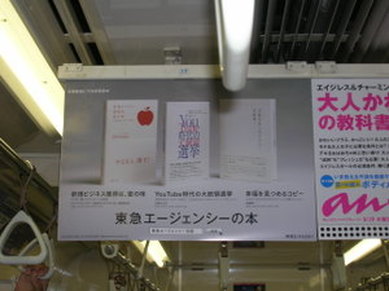今日は、9月11日に開催する、第4回「JaM Media Session in Tokyo」のご案内です。
米国に住んでいて実感するのは、「Twitterの台頭」が象徴するように、ますますソーシャルメディアが、消費者の生活に浸透し、消費者のメディア消費行動やオンラインライフが確実に変化しているという点です。「コンテンツの創出者、ディストリュビュータ、批評家、観察者、またマーケターになる消費者」は、「企業からマーケティングされることを嫌がる消費者」でもあります。今回のセッションでは、リスクテイキングを承知の上で、さまざまな試行錯誤を繰りかえす米国のマーケティング事情をお話ししたいと思います。
定員は40名ですが、前回も参加者の方の活発な発言で盛り上がり、非常にインタラクティブなコミュニケーションが生まれました。ぜひ、皆さまのご参加をお待ちしています。
●セミナー開催概要
JaM Japan Marketing主催セミナー「第4回JaM Media Session in Tokyo」ソーシャルメディアによって変わり行く消費者のオンラインライフ:「Twitterの台頭」が象徴するソーシャルメディアの影響とコミュニケーションの変化に、マーケターはどのような対応をすべきなのか?
日時: 2009年9月11日(金)、18:30開場、19:00開演~20:30終了予定
会場: 株式会社 東急エージェンシー 本社 2階 大会議室
地図
定員: 40名
(応募者多数の場合は抽選と致します。当選のご連絡のみとさせて頂きます。)
受講料: 5000円
(当日領収書を用意していますので、お支払いの時にお渡しします)
献本:参加者には『YouTube時代の大統領選挙ー米国在住マーケターが見た、700日のオバマキャンペーン・ドキュメント』を差し上げます。
申込締切:9月8日(火)
お申込方法:次の参加申込フォームからお申込ください。
お申込 → http://bit.ly/15fY2h