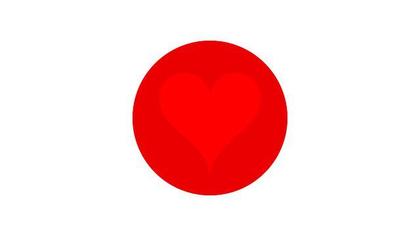
大昔、猪瀬直樹さんの書いたものが好きだった。今日、なんかの拍子に彼のコラムから私が気に入った言葉が出てきた。
「日本人は英語ができないから国際交渉に弱いのではない。日本語ができないからだ。母国語で論理的思考ができない人間が、外国語でコミュニケーション力を発揮できるわけがない~」
これってまさに私が日々実感している言葉。人との意見の相違に直面することを避けて、論理的思考やディベイトを嫌がる日本社会に慣れた人では、グローバルでビジネス交渉はできない。
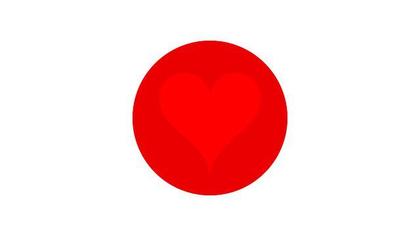 大昔、猪瀬直樹さんの書いたものが好きだった。今日、なんかの拍子に彼のコラムから私が気に入った言葉が出てきた。 「日本人は英語ができないから国際交渉に弱いのではない。日本語ができないからだ。母国語で論理的思考ができない人間が、外国語でコミュニケーション力を発揮できるわけがない~」 これってまさに私が日々実感している言葉。人との意見の相違に直面することを避けて、論理的思考やディベイトを嫌がる日本社会に慣れた人では、グローバルでビジネス交渉はできない。 昨日は、1ヶ月ぶりに自転車に乗って島を24マイルほど走り回りましたが、フェリー乗り場の警備員で60代とおぼしきアフリカ系男性が、私が日本から戻ったばかりと知ると、いきなり「米国は今、日本のために、どんなことをしているのか?」と真剣に聞いてきました。私が米国海軍第7艦隊が「トモダチ作戦:Operation Tomodachi」で被災地救援でがんばっているし、様々な方面から人的支援が集まっていると説明すると、嬉しそうに「それは良かった。この災害は世界中が利害関係を忘れて、同じ人間として一緒に日本を救済支援するための機会だ」と語っていました。また行きつけの店で買い物をしていたら、同じく60代とおぼしく白人女性が「家族は大丈夫?私は地震後すぐに米国赤十字を通して寄付したわ」と、心底心配している風でした。そんな折、そうした普通の米国人の反応とは異なり、日本の大手オンラインサイトで米国在住日本人ジャーナリストが煽るように、米国メディアはこんな風に原発危機を報道しているという記事を見て、極端な書き方に大いに驚き、且つ怒りすら覚えました。
災害事に流言飛語が飛び回るのは世の常ですが、それにジャーナリストと称する人が加担するような動きをするのは納得がいきません。自身の職業を「なんとかスト」と言う以上、マスメディアやブログ、ソーシャルメディアのコンテンツのコピペだけでなく、一般の人たちの地に足のついた意見や情報をきちんと把握した上で、記事を書いて欲しいし、必ずしもNYTやWSJの情報や記事がいつも正しいとは限りません。常に「Breaking news」と叫んでいるCNNはすでにサーカスみたいな感じで、見識ある人は彼らの情報をあまり信頼していませんし、CNNの現地レポートは人的リソースや資金不足で、英語のしゃべれる人しか取材できないので、情報の質はあまり高くありません。 また、私の周囲のごく普通の人たちは、多少の差はあるにしても、当然のようにマスメディアだけに頼らず、ソーシャルメディアを使って、より日本を知っている人や住んでいる人たちから情報をとっており、私も知らないような被災地の人たちの様々なストーリーを知っていました。また、みんな口を揃えて「日本の素晴らしさ」を語っています。日本人ほど、「我慢強く、お互いを助け合い、精神的に強い」国民は他にいない。日本だからこそ、この近年の歴史上最悪とも言うべき大災害で、大混乱もなく、整然と事態の復興にフォーカスできる、これが米国で起こったらとんでもないことになっていたとアタマを抱えています。 そんな中でみんなが口にするは、どの国も政府の官僚主義が事態を悪化させるのは常だが、日本は国民1人1人の人間としての質の高さに反比例して、政府の対応の遅さ、情報の開示の悪さ、さらに諸外国の援助や助言にすぐに耳を貸さない閉鎖性などの問題点を指摘しています。非常時に最も要求されるのは言うまでもなく「リーダーシップ」です。それは通常「目標設定」をした後に、それを達成するために刻々変化する状況の中で、逐次判断をしていかなければならないことで、当然のようにリスクをとりながら実行されます。米国で「リスクをとらないことが最もリスキー」ということがよく言われます。この「リスク管理」の重要性をみんな肌で感じているので、常に最悪を想定してマニュアル作りをします。日本では今でも「言霊信仰」が意識下にあるためなのか、この最悪のことを想定することをみんなが嫌がります。この想定の甘さのツケは危機に陥ると常に露呈されますが、今回もそれを実感します。 世界中の人たちは、真剣に日本のことを憂慮していますし、なんとか力になりたいと真剣に思っています。今朝、Gizmodoが「Why We Love Japan」という非常に彼らしい理由で日本の面白さ、愛すべき部分を記事で紹介しています。私は大きな声で、みんなが「We Love you」と叫んでいることを、日本の人に伝えたいです。しこれは震災がもたらしら「新たな日本の発見」で、あえて言うならば「Japan Renaissnace」ともいうべき、新たな時期を日本は迎えたと思います。日本は過去10年間 「顔が見えない」とか「Japan passing」とか言われて、随分無視されましたが、この震災時の国民1人1人のattitudeで、いきなりHuman Beingとして可視化されています。私は、この辺をこれからもっと話していきたいと思います。 この数字は凄い、思わずため息をつきました。
今朝のAP報道によれば、、ケイマン諸島の「Tax Haven*(租税回避地)」には、1万8857の企業があり、そのうちの半分は、米国所有、米国が請求先住所、あるいはそれ以外の米国関連企業です。ここで米国は、なんと年間1000億ドルの税収を、失っているというリアリティです。これは、GAO(Government Accountability Office)が、Senate Finance Committeeに、調査報告した数字ですが、これは上院議員たちに、何とかしてもらわなければならない大事な税収です。 過去にも、何度もこの問題は、様々な人たちが問題視して、俎上にあげていますが、政府がこの問題にシリアスに、メスを入れた話はきいたことがありません。ずいぶん昔になりますが、私が2002年に書いた「エンロン問題」のコラムでも、以下のようにエンロンはケイマン諸島881の子会社を設立して5年間収益なしとして無税申告して、米国政府から還付金として3億8300万ドルを受け取るという凄さです。 「エンロンの企業体質を表す例としてわかりやすいのが、その税金対策です。アメリカの多くの企業が行っている税金逃れの古典的な手法で、租税回避地(外国の島々)に子会社を持ち所得税をゼロにするやり方です。2000年10月フォーチュン500の半数の企業を対象に調べた「市民による公正な税金のための調査」によると、1996年16社、1997年17社、1998年24社が、子会社を税金天国に設立して無税申告をしています。エンロンの場合は、その数の多さが尋常ではなく881の子会社をつくり、過去5年間4回を収益なしとして報告して無税扱いとなり、さらに政府から還付金として3億8,200万ドルが返還されています。ケイマン諸島に692、トルコとカイコスに119、マルティネスに48、バミューダに8と、まるで乱開発されたリゾートホテルのように税金逃れのパートナー企業を各島々に設立しています。仕組みは意外とシンプルで、利益を米国法律下にないパートナー企業へ送り、パートナーが手数料をとった後おカネがエンロンに戻されるというもので、この場合は米国の所得税申告の対象外になります。」 今朝のこの数字を見ながら、いかに政府が企業の税金逃れに甘いかを痛感しています。米国は、今、以下のような問題を抱えています。
NBC/WSJの調査では、アメリカ人の74%は「米国は悪い方向に向かっている」と回答しています。こうした経済的にかなりダメージを受けているアメリカにおいて、「この企業の税金天国」にみられる「税金の不平等」は、許せないものがあります。マイクロビジネスですが、ビジネスオーナーとして、税金を払うことに苦労している私は、これには怒りを感じます。 アップデイト:「Tax Haven」の日本語訳の「税金天国」が間違っているという指摘を受けて、「租税回避地」と表現を訂正しました。 Utah(ユタ州)は、8月からエネルギーの削減と環境保護を考えて、州政府として初めて、月曜日から木曜日までの週4日1日10時間労働の導入を発表しました。2万4000人の州政府勤務者のうち、1万7000人がこの週4日制の対象者となります。警官、刑務所、法廷、州立大学に勤務する人たちは、この制度の対象外となりますが、70%の人たちが週休3日となります。勤務時間は、午前7時から午後6時までとなるので、一般の人たちは仕事の始まる前と終わった後に、州政府のサービスを利用できるので、これを良しとしており、さらにオンライン活用をより奨励するようにする予定です。この導入によって、予測される削減項目は以下です。
すでに多くの一般企業は社員の通勤コストの高騰を憂慮して、テレコミュート導入を薦めており、社員も自動車通勤から自転車と公共の乗り物による通勤へ変える、就職も自宅からなるべく近い企業を優先するなど、ガソリンの経費がかからないやり方にシフトしています。全米平均1ガロン4ドルを超えたガソリンが今後下がる可能性は低く、多くの人たちは「ガソリン依存」から逃れることを模索しています。これは家計を圧迫するという経済的な要因が大きく占めていますが、さらに米国もやっとメインストリームの人たちが、「いかにGreener(よりエコフレンドリーへ)になれるか?」という意識を持ちはじめたことの現われです。 UPSのガソリン消費削減戦略は非常にシンプル デリバリ会社の大手企業で9万4000台のトラックを所有するUPSは、こうしたガソリン消費削減に非常に積極的で、ちょっとした工夫で、年間300万ガロンのガソリン消費の削減を達成しています。
3番目のクルマへの負荷を軽くするためには、もっと極論すれば、ドライバーや家族がもっと体重を減らせば、燃費が上がると言い方もできます。米国の肥満、およびそれに付随した糖尿病などの疾患の増大は、食べすぎ(食事の量、およびジャンクフードの両方)と運動不足が大きな要因です。この点からも、エコフレンドリーなライフスタイル、すなわち、自転車や公共の乗り物の利用は、こうした運動不足の解消にもつながり、CO2削減にも寄与する、「一挙両得」の考え方です。 アメリカ人は非常にDrastic(思い切った手段を使う)です。合理的で効率的であることならば、多少難しくてもチャレンジしていきます。このユタ州が導入する週4日制は、他の州も大いに注目しており、例えユタで失敗しても、他の州はその失敗を活かして実施していくと思います。夫が以前勤務していたGEでは、随分昔にこの週4日制を導入しましたが(ただし社員の半数は金曜日に出勤する隔週4日制でした)、早すぎたためか継続しなかったようです。今は、家庭内のインフラも整って、多くの人がテレコミュートもできるので、週4日制を私企業が採用しても、最悪は自宅から働けるので、十分実施可能な状況にきています。 夫に「JaMも週4日制を導入しようかしら」と問いかけたら、「すでに週7日24時間体制で働いてる君には実行不可能だ」と、ゲラゲラ笑っていました。確かにマイクロビジネスのオーナーで、かつブロガーである私は、公務員のようにはいきませんが... アメリカ人に最も人気のあるクルマとして、20年以上も首位をキープしていた、フォードのピックアップトラック「F-150」が、ホンダのCivic(シビック)に王座を明け渡しました。
これはガソリン高騰という環境を考えれば、当然と思われるかもしれませんが、アメリカ人にとってピックアップトラックへの想いは、一種独特なものがあります。かつてのミドルクラスのアメリカ人は、自分の家の所有とピックアップトラックはワンセットとも言うべきもので、「Do It Your Self」という文化の中で、多くのツールや修理のための材料をトラックで自宅に運んでいました。 実は我が家にも、夫が1987年に購入した21年も経つフォードのピックアップトラック「Ranger」があります。3年前に今の家(80年以上経った古い家)を購入する前は、ほとんど使っていなかったのですが、購入後は、しょっちゅう、Home DepotやPaganoといった材料や道具販売の店に通って、木材、ペンキ、チェーンソー、梯子、芝刈り機などをトラックで運びました。私は「トラックは、もうドネーションしたら?」と、以前夫に話したこともあり、夫は得意そうに、「だから言っただろう、Home Ownerにとって、トラックは絶対に持っていなければならないものなんだから」と言っています。夫のように大自然の中で育ったアメリカ人にとって、この「Big Blue(我が家ではクルマにニックネームをつけています)」は、利便性もそうですが、もっと感情的にエンゲージしているようです。 今日のWard's Auto Groupの発表によると、5月の販売台数のランキングは、
ということで、燃費の良いクルマが上位を占めています。シビックは、1ガロンあたりの走行距離は29 mpgで、F-150は15 mpgです。年間1万5000マイル走ると仮定して、1ガロン4.08ドルで計算すると、シビックは2111ドル、F-150は4082ドルのガソリン代がかかります(U.S. Department of Energyによる)。この差はかなり大きいものがあります。1年前(2007年5月)と比べると、Fシリーズのセールスは、30%落ち込んでおり、それと反対にシビックは33%、アコードは37%アップしており、消費者のクルマへの志向が、大きく変化していることを示唆しています。 クライスラーは、すでにクルマの購入者に、今後3年間1ガロン2.99ドルのガソリン保証のインセンティブをつけてマーケティングしていますし、GMは6月3日、北米の4つのトラック製造工場を閉めて(1万人の社員がいます)、より燃費の良いクルマ製造を始めると発表しています。また、ガソリン消費の怪物君といった「Hummer(ハマー)」ブランドの売却を考えていると発言しており、米国自動車メーカーは生き残りをかけて、必死です。今年は、フォードのFシリーズの60周年に当たる年ですが、時代は大きく旋回しています。 6/11のエントリで「Clinton(クリントン)が負けた6つの理由」として、以下の要因をあげました。
今日はこの中で、第2番目の理由について書いてみます。 イラク戦争は、イラクが大量破壊兵器を保有するという疑惑に対して、国連の無条件査察を受け入れなかったために、2003年3月19日米英中心にした連合軍がイラクに参戦しました。詳細は別にして、2004年10月アメリカが勝利宣言を行った後、派遣された査察団は、「大量破壊兵器が存在しないこと」を報告して、その後さまざまな証言の中で、ブッシュ政権が当初からこの事実を知りながらも意図的な情報操作をして、開戦に踏み切らせたという疑惑が生まれています。また、戦犯として処刑されたサダム・フセイン大統領とアルカイダとの関係を証明する証拠も発見されず、米国民にとっては、この戦争は「参戦理由のない戦争で、イラク国内の宗教的泥沼に足を踏み入れた」という、大きな不満を呼び起こしています。多くの市民や兵士の死傷者数の増加、さらに莫大なコスト(戦費)は、イラクからの脱出の足がかりのないブッシュ政権への批判を増大させています。 こうした背景の下で、昨年大統領候補選挙がスタートしました。Obama(オバマ)の最も大きなCredential(クレデンシャル:資格推薦状)は、「参戦投票において、自分は最初から反戦を唱えた」という点です。当時は、911の直後で、テロ攻撃への不安が渦巻く中、ブッシュ政権、共和党、民主党のほとんどの人たちが、「対テロ対策」のために、「イラク戦争への参戦を支持する」というムードが蔓延していました。クリントンもご多分に漏れず、賛成投票を投じており、これが今回の予備選で大きな足かせとなって、彼女の「Judgment(判断)」に関する疑問と批判を生じさせました。 ここでのポイントは、彼女はこの「戦争参戦への賛成投票」の「非」を、キャンペーン中に認めなかったことで、何回も言い方を変えて(ある意味で詭弁)、彼女は自分の非を是正しようと試みています。これが、実は大きな誤算で、彼女同様に賛成投票をしたJohn Edwards(ジョン・エドワーズ)は、はっきり自分の非を認めて、後悔の念を表明したのとは異なり、「言い逃れ」をしようとしたクリントンは、「信頼性」を失ってしまいました。 アメリカ人は、「失敗を経験と考える」ので、過ちを素直に認めて、この失敗を活かして、大きく成功する人を尊敬します。シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト(VC)は、失敗を一度もしたことがないアントレプレナーには投資をしないという暗黙のルールがあります。理由は簡単で、大きな見返りを期待するVCにとって、大きな成功をもたらすアントレプレナーは、「リスクをとる(=失敗を恐れない)人」だからです。 米国企業のリスクマネジメントで最も重要なことは、失敗をした際に、即座に行動を起こすことと、真摯な態度でその失敗を認めて迅速に修復作業にかかることです。「起きてしまったことの言い訳」をクドクドされることは、誰もが最も嫌がることです。クリントンの本当のミスは、ミスジャッジをしたことを認めない頑固さと、言い訳で逃れようとしたAttitude(態度)にあったと思います。 ただし、言い方を変えると、政治経験が浅いオバマが民主党大統領候補になれた最も大きな要因は、「反戦投票」にあり、彼のこの「Judgment(判断)」がなければ、彼はクリントンに勝てなかった可能性もあり、クリントンの「賛成投票」は大きな代償を払ったといえます。 今回の米国大統領選挙が、米国のみならず、全世界の注目を浴びていることは、衆目の一致するところです。以下は、Pew Research Centerによる、世界各国の人たちに問いかけた、民主党のObama(オバマ)と共和党とMcCain(マケイン)は、「どちらが大統領になったほうが自信が持てるか?」という質問への回答です。国によって多少の差がありますが、オバマに期待する国が目立ちます。
米国本国は、1%マケインがリードしていますが、アフリカのタンザニアの84%から始まって、ヨーロッパ、アジア、南米の主要国は、オバマ支持のようです。確かに、現在のブッシュ政権への不満は、世界中にくすぶっています。イラク・アフガン戦争、住宅バブルを放置して崩壊を招いた経済施策、地球温暖化対策への不参加など、世界各国との協調を求めようとしない強硬なブッシュ政権への反発は、各国にあります。彼らが新政権に期待するのは、やはり「Change(変革)」です。この実現は、ブッシュ政権の国家保障および経済政策を踏襲するマケインでは、出来にくいことです。 ただし、米国は、他の国の人が思うほど、「リベラル」ではなく、非常にコンサーバティブな考え方を持つ人が多くいる国です。また、生活の中で、キリスト教の占める比重も大きく、オバマが支持する政策(ゲイの法的権利保護や女性の中絶選択を支持する権利など)は、そうしたキリスト教のエバンジェリストたちの非難の的であり、そのハードルはかなり大きいといえます。また、白人と黒人の両親を持つBiracial(バイレイシャル:複数の人種)であるオバマに対する、人種への抵抗はかなりあるのは事実です。アタマではわかっていても、感情面でまだまだ受け入れにくい人もいて、本当にアメリカ人が「黒人大統領」を受容する準備が出来ているのかという大きな疑問は重くのしかかってきます。 予備選挙と異なり、本選挙のある11月までの5ヶ月間、オバマとマケインの間で繰り広げられる戦いは、両者の違いをより鮮明にした、厳しい戦いが繰り広げられます。まさに米国は「選択の時」を迎えている、そんな気がします。 今、突然、Tim Russertの死を、New York TimesのメールのNews Alertで知って、思わず呆然としてしまいました。
彼は、NBCのシニア政治ジャーナリストとして、毎週日曜日の政治討論番組「Meet the Press」の司会を務め、さまざまな政治ニュースでのゲストコメンテータ、大統領候補者選挙のディベイトではモデレータとして活躍する、米国の政治シーンにおける「顔」です。 その彼が58歳の若さで心臓発作で亡くなるとは、昨日まで誰もが予想しなかったことです。彼は、Time Magazineの2008年「100 most influential people in their world(その業界で最も影響力にある100人)」に選ばれており、1984年にNBCに入社して24年間に及ぶキャリアと実績は、非常に大きなものがあります。 私は、彼の落ち着きのある声が好きでした。変に感情的にならず、穏やかなトーンで厳しい質問をする彼を見ていると、冷静な判断と真実をそこに感じて、納得できました。 日曜日に彼を見られなくなるのは、本当に寂しいです。彼は11月の大統領選の結果を、絶対に知りたかったと思います。本当に残念です。 いつも大統領選ネタばかり申し訳ないのですが、毎日かなり驚くことが多くて、思わずブログしています。今日の「驚き!!」は、これです。
Yahoo Newsが共和党の大統領候補者に、単純に「あなたのコンピュータは、PCそれとも Macですか?」と聞いたヴィデオがあります。
これで、なぜマケインが、オバマ陣営に「メディアのモデレイターなし、小さなスペースのタウンホールスタイルのディベイトを行いたい」というリクエストを、「手紙」で送ったかが、わかりました。オバマ陣営のコメントは、「マケインは、なぜEメールしないで、郵送したんだろう?」というのが最初の反応だったそうです。 これって、ジェネレーション(71歳 vs. 46歳)の違いでは済まされない、重要なポイントのような気がします。 ちなみに、Hillary Clinton(ヒラリー・クリントン)はPC、Barack Obama(バラク・オバマ)はMacです、これも納得。 アップデイト:マケインのコンピュータとインターネット活用のスキルは、上述のYahooのインタビューの時より、かなり向上しているみたいです?? 彼は、6/9バージニア州の政治献金のためのパーティで、副大統領選びはどうなっているのか?という質問に対して、「"You know, basically it's a Google," "What you can find out now on the Internet -- it's remarkable."(基本はGoogle。本当に驚くべきことだ。インターネットではどんなことでも探せる)」と、ジョークで答えています。この答えに対して、ブログ圏では、コンピュータが使えないくせに、「グーグルする」というジョークで答えるなんて許せないという批判もあり、マケインは早く自分で操作できるようになったほうがいいと思います。 今日のObama(オバマ)ストーリーは、Bob Dylan(ボブ・ディラン)のコメントです。
現在スカンジナビア諸国のコンサート中のボブ・ディランは、デンマークのOdenseで(ここはアンデルセンの生誕地。うちの夫の先祖はこの街からアメリカに移住してきています。夫と2人と、ぜひこの島に行ってセーリングをしたいと思っている場所です)、「The Times」からインタビューを受けている時に「オバマ支持」の発言をしています。
Generation Y(ジェネレーションY)に人気のあるミュージシャンは、ヒップホップの現代の若手ミュージシャンだけではありません。Gen Yが「Bobs(2人のボブ)」と呼ぶ、「Bob Dylan」とレゲエミュージックのレジェンド「Bob Marley」への憧れは強く、私が仕事で訪問した大学生のアパートメントの壁に、この2人のポスターを良く見かけました。このディランのオバマ支持発言を聞いて、オバマをサポートする若い人たちがなぜディランが好きなのかが納得できます。ディランもGen Yも、社会や人間に関して決して「シニカル」な態度を取らず、「自分たちの力で出来ることがある」という「Attitude(姿勢・態度)」で、真正面から課題に取り組んでいます。 Baby Boomers(ベビーブーマーズ)のオバマ支持者は、若い頃に夢中になった社会変革の夢を思い出し、「もう一度、未来を信じてみようと思った」と言って、「チェンジ」のムーブメントに参加したと語っています。ディランの1964年の曲「The Times They are a-Changin」は、まさに今を語っているようです。 |
大柴ひさみ日米両国でビジネス・マーケティング活動を、マーケターとして、消費者として実践してきた大柴ひさみが語る「リアルな米国ビジネス&マーケティングのInsight」 Categories
All
|