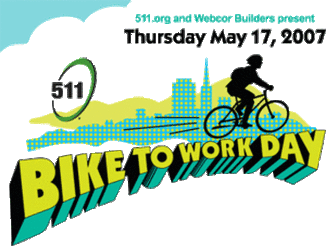今週アタマから、どんな会話が飛び出すかと、メディアやブログで多くのバズが起きていた2人は、ともに51歳となって、旧友が久しぶりに再開したようなフレンドリーな感じで、リラックスした姿をみせてくれました。
2人の好対照なキャラクターは、その服装や話し方にも良く現れていて、スティーブのトレードマークの黒のタートルネックシャツとジーンズ、ビルのブルーのストライプのシャツに黒のパンツというテックギークなファッションは、今さらながらに2人を示唆しています。天才マーケッターのスティーブが話し始めると全ての注目が彼に行ってしまいますが、最初にビルが、「I'm not a fake Stece Jobs(私はスティーブジョブズのまねはしない)」と言って、大いに笑わせます。
おすすめは、プロローグとして、彼らがステージに立つ前に流された、「1983年のマッキントッシュ・ソフトウェア・デーティング・ゲーム」のヴィデオです。27歳のスティーブとビルが登場して、本当に楽しげな様子で、壇上で語り合っています。2007年の2人は、過去30年間の道のりで、お互いにおのおの辛い時期に、助け合ったことを素直に語り、さまざまなジョークの中に歴史の重さを感じました。
2人の関係は?と聞かれて、スティーブは、ビートルズの曲「Two of Us」を引用して、ちょっと言葉に詰まるほど、2人の長い長い30年間の道のりを懐古していました。
"You and I have memories, longer than the road that stretches out ahead."
30年前は、私のようなごく普通の人間が、コンピュータを使うなんて、夢のまた夢の時代でした(私が1979年に新入社員として入社した時に、社内にFaxマシーンもなく、上司が「女の子を、今から行かせます」という言葉とともに、文書を持ってクライアントのところへ走りました。そうです、私は当時のFaxであり、今のEmailの役目を担っていました)。
今日は、2人のヴィデオを見ながら、そんな時代をちょっと振り返って、改めて夢の実現のために走り続けた2人に、心から感謝しています。
PS: スティーブが、「かつてはミーティングルームで最年少だった自分が、今はいつも最年長だ」と発言していますが、これは私がいつも言っていることです。これは、50代に入るとつくづく実感することです。特に、テクノロジー業界は、CEOたちが若く、GoogleのFoundersに代表されるように、Generation X & Yが主流です。Bommersの2人は、やはり時代を感じさせます。