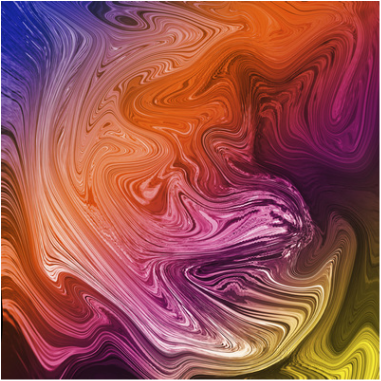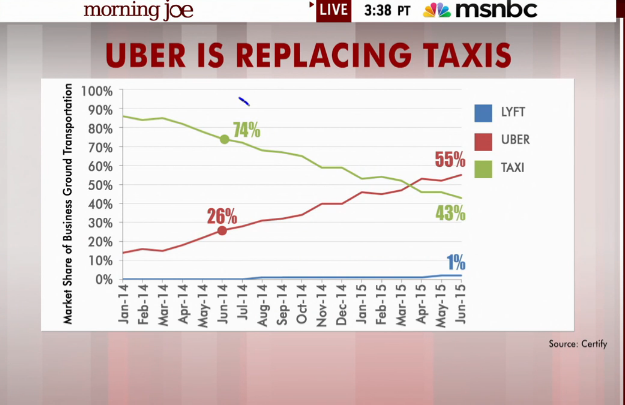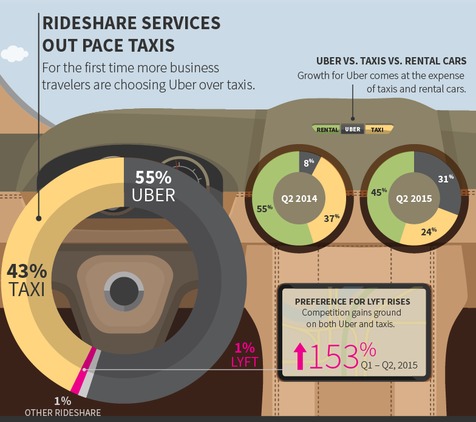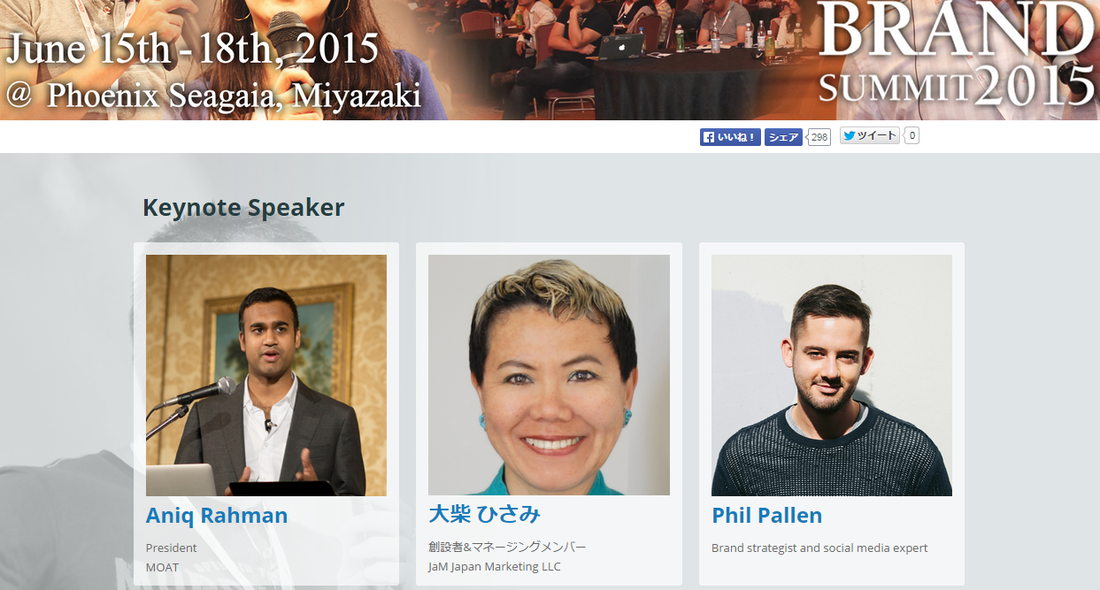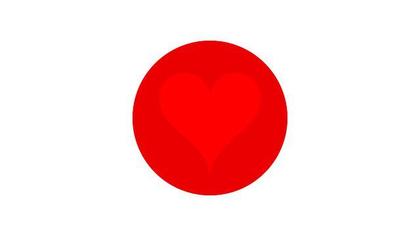創業者のGoogle Boys(Larry Page & Sergey Brin)の2人がどこまでドラッカー教授の言う「チェンジ・エージェントへの変身」を意識したかどうか不明だが、以下は、ダイヤモンド社刊の上田惇生訳「Next Society (ネクスト・ソサエティ)」の第1部第7章に出てくる文章で、これをを読み返すと、彼らのアタマに、こうした考えがよぎったような気がする。
「チェンジ・エージェントたれ」
組織が生き残りかつ成功するためには、自らがチェンジ・エージェント、すなわち変革機関とならなければならない。変化をマネジメントする最善の方法は、自ら変化をつくりだすことである。経験の教えるところによれば、既存の組織にイノベーションを移植することは出来ない。組織自らが、全体としてチェンジ・ エージェントへと変身しなければならない。
そのためには、
第1に、成功していないものはすべて組織的に廃棄しなければならない。
第2に、あらゆる製品、サービス、プロセスを組織的かつ継続的に改善していかなければならい。すなわち日本でいうカイゼンを行わなければならない。
第3に、あらゆる成功、特に予期せぬ成功、計画外の成功を追求していかなければならない。
第4に、体系的にイノベーションを行っていかなければならない。
チェンジ・エージェントたるための要点は、組織全体の思考態度を変えることである。全員が、変化を脅威ではなくチャンスとして捉えるようになることである。
説明の必要もないぐらいに、よく知られた考え方だが、私が改めて注目したのは「変化をマネジメントする最善の方法は、自ら変化をつくりだすことである」という指摘である。これは、成功し続けている組織(=企業)が中々実行できない部分で、これを実行できなかった企業は、俗に言う「大企業病」に陥る。この症状は日米を問わず、世界中に蔓延するビジネス疾患で、大きく成長した企業が一度はこの病理に蝕まれ、うまく脱しきれる場合もあるが、脱しきれずに、ビジネスの成長がとまり、市場の変化に対応できず、沈んでいく、大企業も多々ある。
Googleは、Alphabetの傘下に「Moon Shot Projects(月旅行のように野心的なプロジェクト)」と呼ばれる「Google X Lab」、「Calico」、「Life Sciences 」といった、自律走行車やバイオテクノロジー分野の革新的な事業を組み入れて、本体のインターネット事業サービスから切り離す。CEOにはPage、プレジデントにはBrinが就任して、本体のGoogleから独立して運営していく。このニュースを受けて、Googleの株価は昨日4.10%増の$690.30と上昇した。投資家は、この経営判断を、Warren BuffettのBerkshire HathawayスタイルのGoogleのコングロマリット化とみなし、先が見えにくくInnovativeであるがRiskyな「Moon Shot Projects」が、いつでも切り離し可能となり、さらに事業形態の「Transparency」が高まると、好意的に判断したようである。
今後のAlphabetの動きで、様々な評価が出てくると思うが、私は創業者2人にとって、「Innovation」の持つ意味は大きく、広告収益に依存する既存のGoogle本体のビジネスの中で、彼らがやりたい「革新的な事業領域で革新的な変化」を起こすことの難しさを実感し、組織自らを「チェンジ・エージェントへ変身すべく」、Alphabet創設を選択したのではないかと思う。また、これは言い換えれば成功した大企業が必ず陥る「大企業病」への「危機意識」で、それを防ぐためには、「自らが変化する必要性に迫られた」ともいえる。
私は1999年10月集英社の雑誌「BART」の取材のために、編集者と一緒に日本人で初めてBrinに直接インタビューした経験がある。Googleはその年の8月2500万ドルの資金をVCから調達して、Mountain Viewのオフィスに引っ越してきたばかりで、当時24歳のBrinの部屋には段ボール箱や自転車が置いてあり、スタンフォードの学生の部屋みたいだったのを記憶している。取材後に編集者と2人で「Googleってとんでもない企業になると思う。何とか彼らに投資できないかなあ?」と、暗い駐車場を歩きながら話しあったことを思い出す。あれから16年、まさに予想したとおりになり、あの時の会話にもっと真剣に取り組めばよかったとつくづく実感する。
ドラッカー教授が指摘するように、企業は「チェンジ・エージェント」であり続けなければ、失墜の可能性を常にはらむ。組織全体およびリーダーとなるべき経営者の「変革者」の意識が欠落すると、どんなに優れた企業であっても、成長は鈍化する。GoogleのAlphabet創設は、少なくとも将来を見据えたProactiveな経営判断で、これによって今後示されるGoogleの革新性を、ぜひこの眼で見たいと思う。それは多少でもGoogleと歴史的な行きがかりのある、私の個人的な想いでもある。